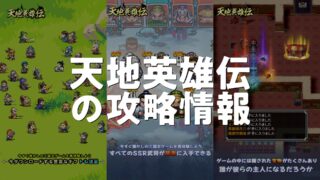ニュースの要約
- 第8回自動翻訳シンポジウムが開催されました。
- 自治体における多言語翻訳技術の活用事例が紹介されました。
- 生成AIを活用した翻訳の実現と社会実装に向けた取り組みが進められています。
概要
2025年2月19日(水)、総務省、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)及びグローバルコミュニケーション開発推進協議会は、「生成AIとAI翻訳 ~自治体での活用~」をテーマに、8回目となる「自動翻訳シンポジウム」を開催しました。
当日は422名が参加し、研究者による最新の技術動向や、開発メーカーによる、各自治体での自動翻訳機器・サービスの活用に関する講演が行われました。また、22者の企業・団体による最新の自動翻訳製品・サービス等の展示も行われました。
基調講演では、大規模言語モデルLLMの特徴や、その活用による「ことばの壁」を超えるメカニズムが紹介されました。また、東京都板橋区での多言語通訳サービスの活用事例や、新潟市の観光イベントでの自動翻訳システムの活用などの講演では、自治体での多言語翻訳技術の実践的な取り組みが紹介されました。
NICT 徳田英幸理事長は閉会の挨拶で、生成AIやマルチモーダル通訳の研究開発にも着手していることを述べ、さらなる多言語翻訳技術の進化と社会実装に向けた取り組みを強化していくと述べました。
編集部の感想
編集部のまとめ
自動翻訳シンポジウム:第8回 生成AIとAI翻訳 ~自治体での活用~を開催しました!についてまとめました
本シンポジウムでは、大規模言語モデルの可能性や、自治体での多言語翻訳技術の活用事例など、様々な知見が共有されました。特に自治体における多言語対応の取り組みは注目に値します。機械翻訳の活用は広がりつつも、人手による検証やガイドラインの活用など、適切な運用が重要であることが示されました。
また、生成AIやマルチモーダル通訳の研究開発にも着手していることからわかるように、多言語翻訳技術の進化はまだ続きます。2025年の大阪・関西万博での実装を見据え、さらなる技術革新が期待されます。言語の壁を越えた自由なコミュニケーションの実現に向け、産官学が協力して取り組んでいく姿勢が印象的でした。
参照元:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000134737.html